- 2024/04/25
- 2024/12/13
ブロックチェーンをどこよりもわかりやすく徹底解説!

「ブロックチェーンってどんな仕組みなの?」という疑問をお持ちの方も少なくないのではないでしょうか。
暗号資産(仮想通貨)の取引を始めたり、興味を持ったりした方の中には、そういった疑問を抱く方もいるかもしれません。
ブロックチェーンは、ビットコイン(BTC)を含む多くの暗号資産で使用されている技術で、情報を記録・管理するために利用されます。しかし、ブロックチェーンは暗号資産に限らず、自動化や効率化などさまざまな取引においても利用される可能性があります。
「ブロックチェーンを学びたいと思い説明を見たものの難しそうに感じる」
「初心者でも理解しやすいように解説されているサイトを見て学びたい」
ブロックチェーンに触れる機会がある場合、ブロックチェーンについての基礎的な知識や利点などを知っておきたいはずです。
そこで今回は、ブロックチェーンの基本的な知識や種類、メリットなどについてわかりやすく解説していきます。

メタバースTipsは、メタバースの最新情報やトレンドを発信する専門メディアです。ビジネスや活用事例に焦点を当てた記事を通じて、初心者から専門家まで幅広い読者に役立つ知識を提供しています。メタバースに関するお悩みやご質問があれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。
▶ メタバースに関するお問い合わせはこちら
目次
ブロックチェーンとは?
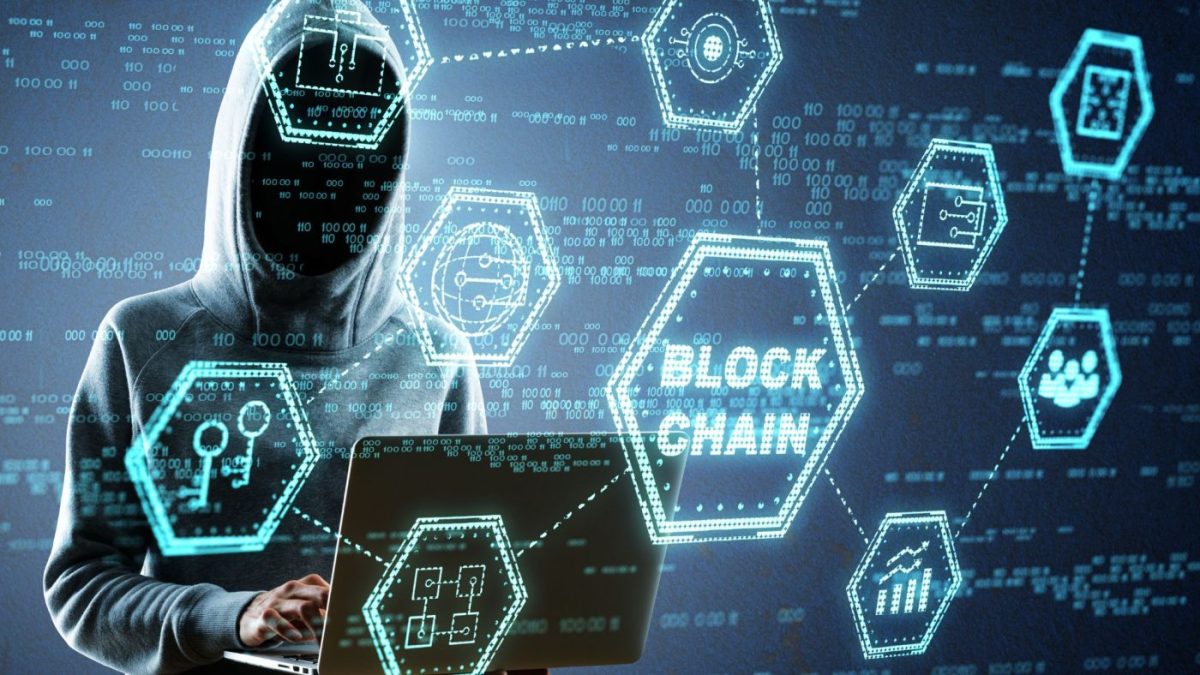
ブロックチェーンとは、情報の記録や管理を目的とした技術で「分散型台帳技術」とも呼ばれています。「ブロック」と呼ばれる取引データを、これまで記録されたデータと鎖のように繋ぎ合わせてユーザーと共有する仕組みです。
ブロックが一度チェーンに組み込まれると、記録の改ざんが難しくなるため、データの安全性や透明性が保たれます。これまでは中央集権的なシステムでの運用が主流でしたが、ブロックチェーンの登場により全てのユーザーがデータを管理できる体制となったのです。
ブロックチェーンの特徴
ブロックチェーンは、伝統的な中央集権型の仕組みとは異なる点がいくつかあります。ここでは、ブロックチェーンの特徴について詳しく見ていきましょう。
管理者やサーバに依存しない
ブロックチェーンは、データを分散型のネットワークにそれぞれ管理し、複数の端末間で通信を行うP2Pテクノロジーのネットワークで構成されている点が特徴です。
主に仮想通貨の取引を行うブロックチェーンでは、システムを1つの場所に置くのではなく、ユーザー同士でシステムを管理する構造になっています。そのため、特定の管理者やサーバに頼らず、1つのノードが故障しても、ブロックチェーン技術を利用する仮想通貨の取引は継続されます。
ネットワークを破壊することは不可
ブロックチェーンは一部のデータが削除されても、他のノードに同じデータが保存されているため復元が可能です。ブロックチェーンを完全に停止させるためには、データを共有している全てのノードを同時に破壊する必要があります。
このことから、ブロックチェーンネットワークの破壊は事実上不可能と言えます。
ハッシュ関数の利用
ブロックチェーンのデータには、元のデータからランダムな文字列(ハッシュ値)を生成するハッシュ関数が使用されています。
ハッシュ関数にて生成されたハッシュ値から、元のデータを復元することはできません。言い換えると、ハッシュ関数は不可逆性を持っていると言えます。
ブロックチェーンでは、前のブロックのハッシュ関数が次のブロックに含まれており、それによってデータがチェーンのようにつながっています。
ブロックチェーンでできること
ここでは、ブロックチェーンの可能性について3つ説明します。
データの改ざん防止
ブロックチェーンは、非常に高い「改ざん耐性」を持っています。データ共有にP2Pネットワークを使用し、ブロックに格納されたハッシュ値を時系列順につなげるデータ構造の両方が、改ざんを困難にするための仕組みです。
また、ブロックチェーンは、PoWを使用して不正が行われていないことを証明し、コンセンサスアルゴリズムを使用して全体の合意形成を確認し、公開鍵や電子署名を使用して偽造防止および暗号化技術を使用することもあります。これらの技術により、ブロックチェーンはサイバー攻撃や内部不正にも強力です。
透明性の確保
ブロックチェーンでは、全ての参加者がネットワークに参加し、共有するデータが同じです。全員が保有する記録台帳により、透明性が常に確保されています。
この特徴は、従来の第三者機関を介した取引とは異なるものです。
トレーサビリティ
トレーサビリティは「追跡可能性」を指す概念です。
通常のシステムでは、トレーサビリティを確保するためには、複数のシステムのデータを統合する必要があります。しかし、ブロックチェーンでは、すべての取引履歴がブロックにデータとして格納され、その情報は参加者が常にアクセスできるため、データの統合が不要で、個々の取引を追跡することができます。
ブロックチェーンの種類

ブロックチェーンは「パブリック型」「プライベート型」「コンソーシアム型」の3つに分類されます。それぞれの違いを極端に表すと、「管理者の有無」によってブロックチェーンの種類が分かれる仕組みです。
以下で一つ一つ、詳しくみていきましょう。
パブリック型
パブリック型ブロックチェーンは、管理者が存在しないブロックチェーンの一種です。
例えば、ビットコインなどの仮想通貨では、主にパブリック型のブロックチェーンが利用されており、情報が完全に公開されているため、透明性が高いというのが特徴です。
一方で、ブロックチェーンのルールを変更したい場合には、管理者が存在しないことから合意形成が困難となる面もあります。また、プライベートな情報も公開されてしまうため、個人情報などの機密性の高い情報のやり取りには適していないというデメリットを持ちます。
一般的に、ブロックチェーンと言えばパブリック型を指すことが多いため、開発や外部委託の際には、どのタイプのブロックチェーンを希望しているかを明確に伝えるようにしましょう。
プライベート型
プライベート型は、パブリック型とは異なり、ブロックチェーンの管理者が存在します。
利用できるのも管理者から許可された方のみであり、不特定多数ではありません。
この形式は分散型ではなく、中央集権型に近いですが、ブロックチェーンの技術を利用しているため、プライバシーや個人情報の保護と管理が容易になります。
また、パブリック型では難しかった情報の管理も行えます。さらに、管理者の存在により、ルールや設定の変更も円滑に行うことが可能です。
コンソーシアム型
コンソーシアム型は、パブリック型とプライベート型の特徴を兼ね備えたタイプです。
プライベート型と同じく、利用は許可された方に限られますが、管理者は複数存在します。
また、コンソーシアム型は特定の参加者のみが関与しているため、プライバシーの保護が容易です。
ただし、複数の管理者がいるため、ルールや運用方針の変更にはプライベート型よりも合意形成に時間がかかる場合があります。さらに、複数の企業が協力してプラットフォームを開発するケースもあり、他社との連携が開発段階から必要となることもあります。
ブロックチェーンのメリット3選
ブロックチェーンには以下のようなメリットがあります。
- システムを安定して利用できる
- 取引の透明度が高い
- 海外送金における手数料が安い
ここでは、上記3つのメリットについて解説します。
システムを安定して利用できる
ブロックチェーンは、データの損失を防ぐことができる堅牢な技術なので、システムを安定して利用することができます。
通常のシステムでは、分散されたデータは個人や企業が管理しており、個々の利用者が必要に応じてデータを取り出すことができます。しかし、この場合、データを保持している人や場所が不透明であり、データの場所を変更する場合には探す必要があります。
しかし、ブロックチェーンを使用すると、同一のデータを完全に独立した複数のシステムに保管することが可能です。これにより、障害が発生してもデータを保護する可能性が非常に高くなり、損失を起こしにくくなります。また、全体の承認を得ることでデータの正確性を証明し、改ざんや偽造を防ぐことができ、システムの安定性を確保することができます。
取引の透明度が高い
データをブロックチェーンに保管する場合、個々のシステム内で同じ台帳情報として保管されます。つまり、利用者はいつでも誰がどのような取引を行ったのかを確認できるということです。
例えば、ビットコインの場合、取引の内容や金額を確認することができます。ただし、第三者はこの情報を知ることはできず、セキュリティは守られたままです。
また、ブロックを少しでも変更すると、ハッシュ値に異常が生じます。このため、データの改ざんがあればすぐに検知され、不正な利益を得ることはできません。ブロックチェーンは取引の透明性が高く、個人情報の保護にも役立つ安全なデータ保管手段といえます。
海外送金における手数料が安い
ブロックチェーンは、海外送金における手数料を削減するためにも役立ちます。なぜなら、海外送金の際には送金インフラのシステムが稼働し、多くの手数料が必要とされるからです。
仮想通貨であるビットコインを使用すると、ブロックチェーンだけで送金が完了するため、余分な手間を省き、手数料を抑えることができます。実際に、銀行同士の送金サービスや仕組みでもブロックチェーンが活用されており、迅速かつ手数料を抑えた便利な方法としてますます利用されていくでしょう。
ブロックチェーンのデメリット2選

様々なメリットがあるブロックチェーンですが、以下のようなデメリットも存在します。
- 処理に時間がかかってしまう
- 記録の変更・削除が困難
ここでは、上記のデメリットについて解説します。
処理に時間がかかってしまう
ハッシュ関数を用いてハッシュ値を算出する処理に時間がかかることがあります。
データの量が増えると、ハイスペックなコンピュータを使っても処理時間がさらに長くなる可能性があります。ビットコインのようなPoWの特性を活用することで、報酬を得るために処理を早めようとする人々が現れるでしょう。
しかし、ある程度の処理スペックで続けている場合、いつかは処理に時間がかかるなどの問題が生じるかもしれません。ブロックチェーンは強固な技術ですが、処理に時間がかかり反映が遅いことを覚えておいてください。
記録の変更・削除が困難
ブロックチェーンによって保管された記録は、消去や変更が不可能なため、セキュリティが確保されています。しかし、この柔軟性の低さは、メリットと同時にデメリットでもあります。
そのため、ブロックチェーン上に重要な記録を行う際には、消去や変更が不可能であることを意識し、慎重に行う必要があるのでよく注意しながら記録を行ってください。
ブロックチェーンの活用事例4選
上記の特徴やメリットに基づき、ブロックチェーンの活用領域と実際の活用例をご紹介します。
①仮想通貨
仮想通貨(暗号資産)は、ブロックチェーン技術を活用して実現された画期的なシステムです。
従来のインターネット上の決済では、銀行などの金融機関のシステムを利用する必要がありました。しかし、ブロックチェーンを利用すれば、金融機関を介さずに送金者と受取人の2者だけで決済を行うことができます。
最初に登場したのはビットコインであり、それ以降、多くの仮想通貨が誕生しました。また、ブロックチェーンの仕様もさまざまなバリエーションが存在しています。
②食品トレーサビリティ
トレーサビリティは、食品業界において非常に重要な要素です。
食の安全確保や品質管理を実現するために必要不可欠であり、業務効率を向上させるためにも役立ちます。しかし、加工品である食品の場合、原材料の数が増え、生産地もグローバルに広がるため、トレーサビリティの追跡や把握は非常に困難です。
そこで、ブロックチェーンを活用した食品サプライチェーンの情報共有が試みられています。ブロックチェーンを活用することで、トレーサビリティが促進され、サプライチェーンの健全化が実現が可能です。
実際に、すでにブロックチェーンベースの食品監視システムを導入し、運用を開始している企業も存在します。食品分野でのブロックチェーンの実用化が進むと、他の業界でも活用の動きが広がることが予想されます。
③著作権保護
音楽、映像、コミック、テキストなどのデジタルコンテンツの著作権を守るために、ブロックチェーン技術が活用されています。欧米では、ミュージシャンと消費者の間で音楽ストリーミングなどを通じて決済が行われるサービスが開始されています。
デジタルコンテンツの売買や貸与などの取引履歴をブロックチェーンに記録し、管理することで、真正なものとコピー品を明確に区別することが可能です。不正なコピーまたは利用があった場合でも、いつどこで不正が発生したのかを特定することが容易になり、さらに著作権料の配分も自動化されるため、ブロックチェーンと関連する技術である「スマートコントラクト」が活用されています。
日本でも、デジタルコンテンツの著作権を管理・保護するサービスが稼働しています。
著作物の情報をブロックチェーンに記録すると同時に、機械学習を使用して著作権を侵害しているウェブサイトを探索し、その情報を証拠としてブロックチェーン上に記録を行っています。
④米国の大統領選
2017年から2018年にかけて、いくつかの実験的な選挙システムブロックチェーンの活用事例があります。
2018年11月には、米国のウェストバージニアで初めてのブロックチェーン投票が実施されました。この投票は、海外駐在軍人約1000人を対象に行われ、実際に投票したのは144人でした。
2020年には、米国大統領選挙の本選挙で初めてブロックチェーン投票が導入されました。ユタ州でスマートフォンの投票アプリを使用した投票が行われた事例です。
かつて米国では、郵便投票や不在者投票において集計作業の遅れや不正投票の可能性が問題視されていました。しかし、ブロックチェーン投票はデータ改ざんのリスクが非常に低いため、選挙に適した技術とされています。
ブロックチェーンの課題と今後
ブロックチェーンの将来に待つ世界は一体どんな世界なのでしょうか。ここでは、ブロックチェーンが持つ課題と今後についてみていきましょう。
ブロックチェーンの課題
ブロックチェーンの課題として特に深刻なのはスケーラビリティの問題です。スケーラビリティとは、トランザクション処理量の拡張性を指し、一度に処理できる取引記録の上限です。
多くのユーザーが一度にブロックチェーンを利用すると、ブロックチェーンの処理能力が落ちてしまいます。トランザクションの遅延が起きるとユーザーは早くトランザクションを処理しようと手数料を高く設定してしまう事態へと発展し手数料の高騰を招いてしまいます。
スケーラビリティの問題が解決しない状態が続くと仮想通貨取引にも影響が出るため、早急な対策が必要です。
ブロックチェーンの今後
ブロックチェーンの未来を考慮する際に絶対に欠かせないのは、DX(デジタルトランスフォーメーション)という概念と、その前提条件であるIoTとAIという2つの要素です。
DXとは、「ITの普及が人々の生活をあらゆる面で向上させる」という考えを指し、ブロックチェーンの活用方法としても高い期待が寄せられています。
DXは、ビッグデータの活用を前提としています。
そして、IoT、ブロックチェーン、AIという3つの要素は、この「ビッグデータ活用を前提としたDX」という大きな社会的動向において、以下のように相互に関連づけることができます。
・ビッグデータを収集する → IoTによるハードウェアデバイスでのデータ収集
・ビッグデータを保存・管理する → ブロックチェーンによるデータベースの統合・管理
・ビッグデータを分析する → AI(機械学習)による大量情報の処理
・ビッグデータを活用する(社会実装する)
このように、ブロックチェーンの将来は、ビッグデータを活用したDXという大きな枠組みの中で、IoTやAIといった相補的な技術と協力しながら、これまで十分に活用されていなかった大量のデータを分析するためのデータ基盤として進化していくでしょう。
そして、その結果として、ブロックチェーンは、産業や社会全体の仕組みを大きく変革し、効率化し、私たちの生活をより豊かにする可能性を秘めています。
ブロックチェーンはメタバースでどのように活用されるか

仮想空間と呼ばれる現実世界とは異なる空間で交流や経済活動ができるメタバースにおいても、ブロックチェーンが活用できます。
ここでは、ブロックチェーンやNFT、暗号資産がメタバースでどのように活用されるのか解説します。
メタバースにおけるNFTの応用方法
NFTは、メタバースと非常に相性が良く、メタバースでの経済活動の発展に貢献すると考えられています。
最初に挙げられるのは、メタバース上でのデジタルアセットの権利保護です。メタバースでは、アバターやアバター用のデジタルファッションアイテムなどが取引されています。これらのアセットは、従来の方法では管理や取引が容易であり、デジタルデータ自体が価値を持ちにくいという課題がありました。
しかし、NFTとしてこれらのデータを管理・取引することで、そのデータの唯一性を証明し、複製を困難にすることができます。これにより、データに価値が生まれ、経済活動が促進されると考えられています。
次に、NFTがメタバース間での相互運用を実現することができる点です。
NFTの特徴は、データ自体を特定の会社のプラットフォームに依存せずに管理できることです。この特徴を活用することで、異なるメタバース間でデジタルアセットを持ち運ぶことが可能になります。データの相互運用の仕組みにより、マルチバースの実現に貢献できると期待されています。
【自治体×NFT】地方創生に役立つNFTの活用事例9選 | メタバースtips
メタバースにおける暗号資産
NFTと同じく、メタバース内の経済活動においては、暗号資産の活用が予測されています。その理由は、メタバースの運営者やチーム(DAOなど)が独自の暗号資産を発行することで、メタバースの発展を促進できるからです。
有名なメタバースで発行される暗号資産としては、The Sandboxの「SAND」やDecentralandの「MANA」が挙げられます。これらの暗号資産を発行することで、メタバースの運営者やチームは運営資金を確保し、メタバースの成長に向けた投資を行うことができます。
ブロックチェーンがメタバースの構築に与える影響
メタバースの最終形であるオープンメタバースの実現には、ブロックチェーンの活用が欠かせません。オープンメタバースは、複数の組織が運営するメタバースであり、特定の組織によって運営されるクローズドメタバースとは異なります。
オープンメタバースの世界では、複数のメタバース間でデータを移行することが可能です。これに対して、クローズドメタバースでは、組織が運営を終了したり、悪意のある操作を行ったりするリスクがあるため、オープンメタバースの実現が期待されています。
オープンメタバースの実現には、ブロックチェーン技術が有効に活用されることが考えられます。具体的には、従来の国家や企業が管理するサーバーではなく、ブロックチェーンシステム上にメタバース空間を構築することで、ユーザー自身が情報を管理したり、取引を行ったりすることが可能です。
まとめ

今回は、ブロックチェーンについてわかりやすく解説しました。
ブロックチェーンとは、情報の管理や記録を目的としており、「ブロック」と呼ばれる取引データを鎖のように繋ぎ合わせてユーザーと共有する技術です。
管理者やサーバーに依存しないほか、ネットワークの破壊がしにくいといったメリットがあります。一方で処理に時間がかかるなどのデメリットも存在します。
メタバースにおいてもブロックチェーンの活用が進んでおり、メタバース上にブロックチェーンのシステムを構築して運用する動きも今後増えてくるでしょう。
メタバースの活用を検討している方は、ぜひ株式会社リプロネクストにご連絡ください。リプロネクストでは、自治体や企業向けにXR・メタバースを提供しており、全国的に注目を集める事案などにも参加しております。
企画から開発、運営までトータルにサポートし、皆さまと共に新たな世界を築いていくことを楽しみにしています。もしメタバースにご興味がありましたら、お気軽にリプロネクストまでお問い合わせください。


「Metaverse tips」は株式会社リプロネクストが運営しています。
ビジネスシーンにおけるメタバースの活用や、導入をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。












